ぽとぽとはらはら 10
伊神 権太
連載全部を読む⇒『ぽとぽとはらはら』
連載前回を読む⇒『ぽとぽとはらはら』9
10.
その日、満はたまたま自身も社交ダンスのレッスンに挑んでいる事実を打ち明け、ブルースを少しだけ踊ろう―ということになり、フラワーパーク江南敷地内の一角でスロー、スロー、クィック、クィックと美智を抱き寄せるようにして少しだけ、一歩・二歩、三歩・四歩…と、踊ったのである。満に密着した美智はステップを踏むごとに若返り青春時代に少し戻ったようで、やがて全身から微かな芳香をかもし、肌の感触もことのほかやわらかで小学生のころとは別の、成熟しきった甘酸っぱさが、そこにはたち上がっていた。
フラワーパーク江南で美智と会って数日後。
満は、こんどは昭和三十九年春に江南市内の私学の高校を卒業した当時のクラスメートの集まりである「二石会(にせきかい)」=二石会の名は、当時二クラスだった普通科担任の二村、石田両先生の頭文字を取り、このように名付けた経緯がある=の呼びかけによる木曽川の昼鵜飼見物に足を運んだ。「二石会」では二年に一度、母校訪問などのこうした粋な催しを続けてきているが、この日集まったのは、まさに高校三年生のころに舟木一夫の青春歌謡「高校三年生」が大ヒットした、その只中で若き日々を過ごしたかけがえのない懐かしの同級生ばかりである(もっとも何人か、は。それも優秀だった人物に限って病気で既に他界してはいたのだが)。
満自身、木曽川河畔の町・江南に住んでいながら、こうしてすぐ近くにある国宝犬山城直下での昼鵜飼観覧をするのはそれこそ、生まれて初めてのことで、出来たら妻の梢や美智にも見せたいな、と心底から思った。その日は朝のうち降っていた小雨もいつのまにか止み、木曽川船着き場で満たちが観覧船に乗るころには、空も晴れ、絶好の日和となっていた。

(鵜飼御膳を食べながら話に興じるクラスメートたち 撮影・たかのぶ)
船内で鵜飼御膳を食べ終えると、いよいよ昼鵜飼の本番で観覧が始まった。水面を滑る如く滑走する鵜たちは、どれも互いに負けじ、と競いながら鮎をとことん追ってやまない。そして鮎を見つけるや、顔を水中深く潜らせ、鮎を得た鵜は、そのつど鵜匠の見事な綱と喉さばきで獲物をそっくり空中に吐かせられるのである。そんな彼女たちを目の前に満は、人間も、鵜も、鮎だって皆、一緒。みんな〈生〉を与えられたそれぞれの営みのなかで懸命に生きているのだ―と至極、当然なことをあらためて思ってみたりした。
やがて鵜たちの喧騒が治まると、船内では高校時代のあんなこと、こんなことに話が弾み、満も高校生に戻った気持ちで話の輪のなかに入り、アレヤコレヤと過ぎし日を回想し、語り合ったのである。船内には、今や美智とはレッスンでダンスを数限りなく踊ってきているはずのあの〝和尚〟の顔も見られた。ほかに、マサルも、ヒロカズも、イタツ、カズヨもいた。みんなホントに楽しそうだ。

(鵜匠の見事な手さばきに鮎を吐き出す鵜 木曽川うかいは1300年の伝統漁法を今に伝える 撮影・たかのぶ)
この日。船内の昼鵜飼観覧の場には、嫁ぎ先の静岡県湖西市から久しぶりに訪れた陽子の姿も見られた。幸せそうでどこか華やいだ感じで、小学生の時にはお人形さんみたいに輝いていた陽子は昔の笑顔そのままに明るく振る舞い賑やかな雰囲気のなか、楽しい時間が過ぎ去っていった。陽子は満とは同じ北小学校卒ではあったが、美智や満とは隣村の勝佐だった。陽子も美智も学校自慢といえるほど可愛い女の子で成績もよかったが、それぞれの家の事情もあって、中学は私学と公立に枝分かれし、それっきり交友は途絶えたままだったという。
それはそれとして。昼鵜飼をひと通り見終えたところで突然、大きな声が水面を走り、割るように轟き、響きわたった。
「おい、おまえら。オレらのときは、舟木一夫や姿美千子、高田美和、倉石功らあのころの青春スターがオレたちの高校で『高校三年生』のロケをやっとったがや。俺、よおぅ、覚えとるよ。あのころはキー坊がいてカマキリ、ハチに。それとひさの先生らもいたよな。今から思えば随分と受験勉強で絞られはしたが、皆、エエじんばかりだった。ここは、みんなで〈高校三年生〉でも歌おまいか」
昼鵜飼をひと通り見終えたところで突然、大きな声が一帯に響き渡った。亀井、かつらの絶叫にも似た声である(亀井は桂という名前だったので〝かつら〟〝かつら〟と呼ばれていた)。ここで断っておくが、キー坊は時の校長・丹羽先生、カマキリは理科の小島先生、ハチは英語の伊藤先生で、ひさの先生は国語教師の西村ひさのさんのことである。

(母校敷地内に今も立つ名物校長だったキー坊、すなわち丹羽喜代次先生の銅像 撮影・たかのぶ)
そして。〝かつら〟の声に合わせ号令でもするように誰かが「おい、〝和尚さん〟。いいな」と言うが早いか、〝和尚〟自らが船内中央に進み出て立ち、右手を指揮棒代わりに斜め上下に振り始めたではないか。気がつけば、彼を真ん中に全員一斉に♪赤い夕陽が校舎をそめて、ニレの木陰に弾む声 ああ~、あ~ぁぁ 高校三年生……と、歌い始めた。「ほんなら、俺がハーモニカをふいたるわ」と立ち上がったのが満で、彼もハーモニカを伴奏でふき始め、船内には興奮が満ち溢れ、異様な雰囲気と熱気に包まれたのだった。
【11へ続く(不定期で連載していきます)】
著者・伊神権太さん経歴
元新聞記者。現在は日本ペンクラブ、日本文藝家協会会員。
脱原発社会をめざす文学者の会会員など。ウエブ文学同人誌「熱砂」主宰。
主な著作は「泣かんとこ 風記者ごん!」「一宮銀ながし」「懺悔の滴」
「マンサニージョの恋」「町の扉 一匹記者現場を生きる」
「ピース・イズ・ラブ 君がいるから」など。
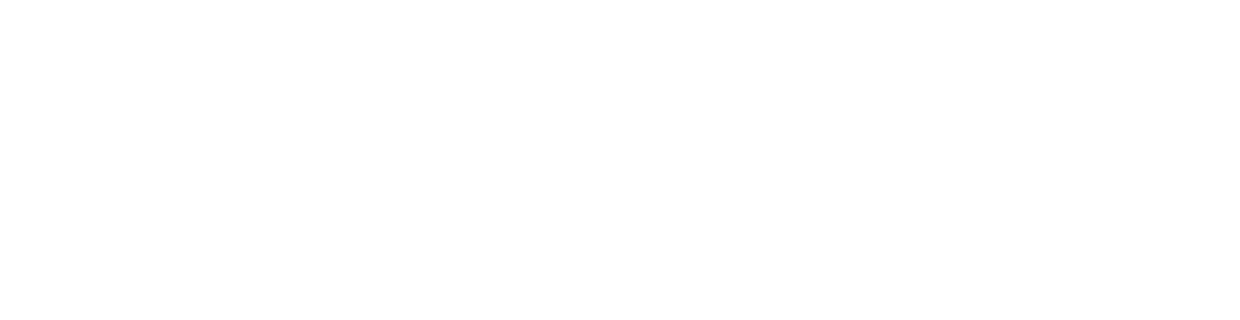





コメント