ぽとぽとはらはら 19
伊神 権太
連載全部を読む⇒『ぽとぽとはらはら』
連載前回を読む⇒『ぽとぽとはらはら』18
19

(届いたチョコには信楽焼の狸さんもびっくり 撮影・たかのぶ)
令和二年二月十四日。バレンタインデーである。なのに、新型コロナウイルスによる肺炎(COVID19)の発症と感染は依然、際限なく広がりつつある。
木曽川河畔に田畑が広がるここ尾張名古屋は江南の一隅・和田で育った満だが、この齢になって郷土の都市開発、いやわが町のありようにまで頭を巡らす、だなんて。自分で自分という存在が皆目わからなくなってきた。思いはさらに何かに弾けるが如くに想念の破片という破片が脳天部を突き破り、そこいら中に飛び散る。昔にぎやかだった街通りはさびれ、一体全体、この町はどこにいってしまったというのか。今では映画館ひとつないじゃないか。

(雲ひとつない空の下、満は来し日々をあれやこれやと考えた 撮影・たかのぶ)
満はいま、青春時代の〝夢んなか〟にいる。夢という川の流れの中でアップアップしながら手足をばたつかせてどこかの岸辺に泳ぎ着こうとしている。それは木曽川なのか。琵琶湖、黒潮洗う太平洋は熊野灘か、それとも波の花が舞う日本海なのか。どこなのか、は分からない。
AI(人工知能)がなにさ。何だ、というのだ。この世の中は今やAIという闖入者に侵されつつある。とうとう新聞小説にまで出て、それっ、アバターがどうのこうの、と個人の生き方につき物語を展開しようとしている。そうではないのだ。この世に何より必要なのは人の温もりなのだよ。満は足をバタつかせながら人間とは、もっと大きなものでなくては。自分の目で見、耳で聞き、足で歩いていかなければ。このままでは人間が人間たる価値を身ぐるみ剥がされてしまうのではないか、と。そんなことを思うのだ。
満。木曽川河畔で少年の日々を育ち、この町をどこまでも愛している。その彼はことし六月一日には満百歳になる母千代からなぜか、幼いころから「ミ・ツ・ル。おまえは文がうまい、うまいのだから。トンチもあるし算盤だって飛び抜けて上手で、負けない。おかあちゃんはおまえのことを十分、知っているからね」とことあるごとに、暗示にでもかけるように褒め続けてくれた。不思議なものでそう言われると自分ではそうは思っていなくとも「そうならなきゃいけない」という感情に襲われることも事実だ。
満州の奉天(現瀋陽)に生まれ、戦争はもう終わったはずなのに突然侵攻してきたロスケ(ロシア)どもから頭を丸坊主にして逃げまわり、生後13日目にして葫芦島から引揚船に乗り、舞鶴経由で千代の実家のある和田に引き揚げてきた満。彼とて他の人と同じように、多くの艱難辛苦が待っていた。その重い扉をひとつひとつこじ開け、両親はじめ兄妹ら家族の愛にも支えられ、ここまで生きてきた。
前にも一部触れたが、高校時代の足の骨折。受験での大敗。学生時代の駅での突然の転倒と入院。別れ。出会い。志摩半島での駆け落ちなど。満とて、人並みに人生劇場を歩んできたことは確かだ。なかでも梢との阿児での逃亡記者生活はじめ、人には言えない多くの困難が目の前に何度も立ちはだかった。満はそんな自らの半生を行ったり来たりしながら、いまも自分だけの〝夢んなか〟にいる……。

(バレンタインデー商戦華やかなショッピングセンター 撮影・たかのぶ)
そして。バレンタインデー。毎年この日に合わせる如く人生の扉は、少しずつ開け放たれた。昭和、平成と駆け抜けてきた満は、この日が来ると忘れられないことが多い。これもミ・ツ・ルの若き日々の思い出といえようか。
小牧で航空記者でいたころ。決まって空港で、エアライン各社で、市役所で、警察で、と取材の先々でチョコレートを渡され、断りきれないままにポケットというポケットがパンパンに満たされることがしばしばだった。だが、一番の思い出となると、能登半島の七尾にいたころ、バレンタインデーやクリスマス・イブになると、決まって七尾市魚町の自宅ポストに満あての郵便物が届いたことである。
郵便物にはハモニカやニューミュージックの録音カセットテープといった満が一番喜びそうなものが入っており、ある年など岡村孝子の【夢をあきらめないで】のカセットを目の前に感激したことを覚えている。差出人は、いつも同じ字体で〝葉子〟となっており、マス目の入った原稿用紙には「時々は、あたしのことも思い出して下さいネ」などと書かれていた。心当たりに聞いても皆、違うと言うので礼をしようにもしようがなく、正直困り果てたのである(詳しくは日本ペンクラブの電子文藝館収録の伊神権太の小説【てまり】を参照されたし)。振り返ればそんなこともあった。

(今も大切に愛用している謎の葉子さんから届いたハモニカ 撮影・たかのぶ)
満は最近、こうして生きている自分が不思議でならない。こんなにも長い間、心臓がただの一秒とて止まることなく動き続けている。なぜか、と思うと同時に当然のことではあるが、この世で生きているものは皆、一生懸命にけなげに生きているという、そうした事実に対する実感である。だから。この世に住む誰もが懸命に生きているのだと思う。
そんなある日のことである。級友の、あの和尚から一本の電話が入った。満がこれまでにない動悸を覚えたのはその時だった。
【20へ続く(不定期で連載していきます)】
著者・伊神権太さん経歴
元新聞記者。現在は日本ペンクラブ、日本文藝家協会会員。
脱原発社会をめざす文学者の会会員など。ウエブ文学同人誌「熱砂」主宰。
主な著作は「泣かんとこ 風記者ごん!」「一宮銀ながし」「懺悔の滴」
「マンサニージョの恋」「町の扉 一匹記者現場を生きる」
「ピース・イズ・ラブ 君がいるから」など。
「しえなんカード(名刺)を置きたい!」「うちも取材してほしい!」という
会社やお店の方がいらっしゃいましたらご連絡お待ちしています♪
「情報提供・お問い合わせ」
・Facebook、twitter または konanjoho@yahoo.co.jp まで
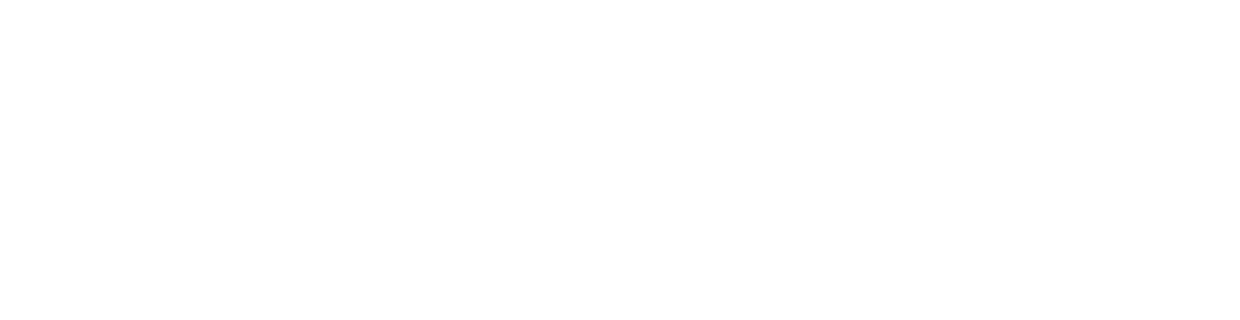



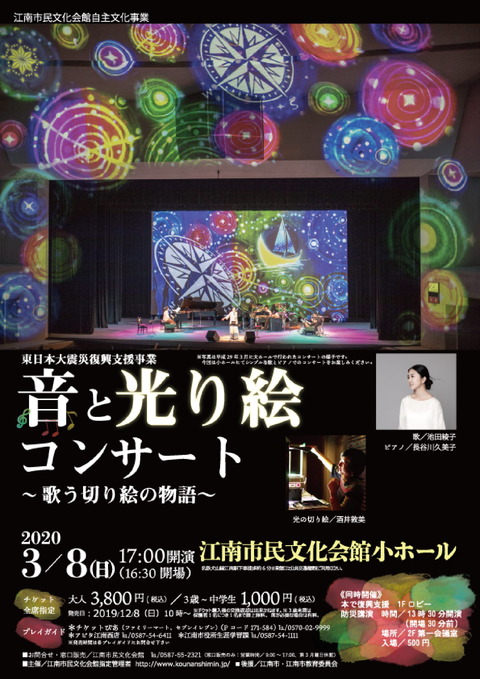
コメント